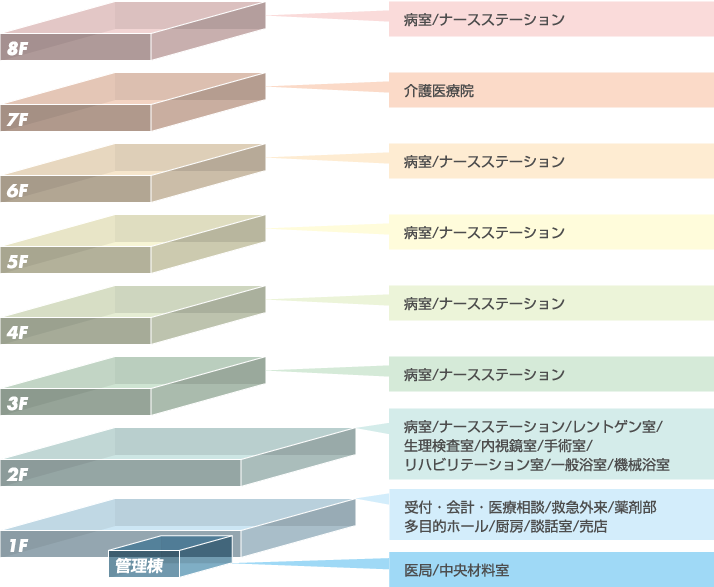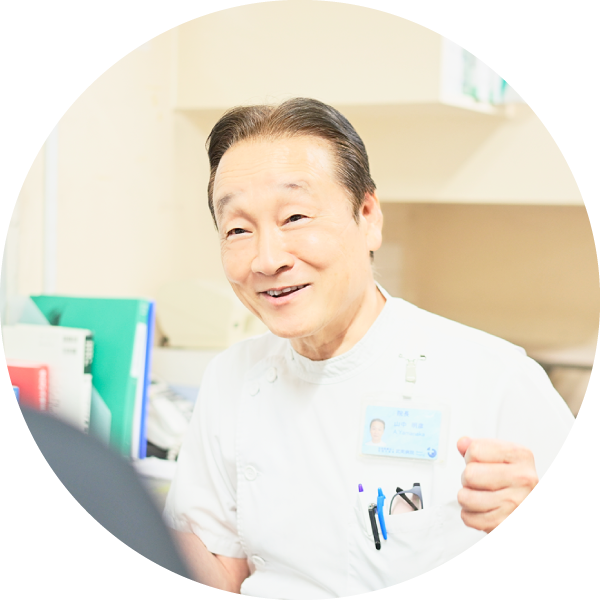
理事長/院長 山中 明彦
武南病院がこの地に根を下ろして以来、私たちの根底に流れ続けているのは、先代院長から受け継いだ「どんな時でも地域医療の最後の砦でありたい」という救急医療への強い意志です。
一方で、日常の健康相談から専門的なケアまで、安心して頼っていただける地域の窓口として、附属クリニックが健康診断や婦人科、歯科など幅広い診療を担っています。
このクリニックと病院本体が密に連携することで、皆様の生涯にわたる健康を切れ目なく支えていくこと。
それが私たちの目指す医療の姿です。
その理想を実現するために、私たちは医療を三つの価値で捉えています。
一つは、的確な「治療内容」。
二つ目は、患者さんの不安な時間を少しでも短くするための「待たせない迅速さ」。
そして三つ目が、心に寄り添う「温かい接客」です。
特に、迅速さと温かさは、私たちが常に自問する「もしこの患者が自分の家族だったらどうするか」という問いから生まれる、最も大切な価値だと考えています。
こうした想いを実現するためには、スタッフの力が不可欠です。
幸い、当院には穏やかで人柄の良いスタッフが多く集まっています。
私たちは、その優しさを土台にしながらも、現状に満足することなく「どうすればもっと患者さんのためになるか」を考え、失敗を恐れずに挑戦する姿勢を大切にしています。
それは、単に日々の業務をこなすのではなく、一人ひとりの仕事が地域全体の安心を支えているのだという、大きな使命感に繋がると信じているからです。
これからも、地域のクリニックの先生方からの声に応えられる後方支援の役割を強化し、誰もが安心して暮らし続けられる医療の実現に貢献してまいります。